自分でお片づけができるようになってほしい!
そう思ってはいるけど…
自分だって片付けは苦手だし、どうやって教えたらいいのかわからない。
学校の家庭科では習うはずだけど…授業は5年生から。
できればもっとはやくからできるようになってほしいですよね~
そうなると,おうちで教えてあげるしか道はないんです!
そこで!
3歳から5歳くらいの幼児を対象にした「子供の将来につながるお片付けの教え方」を4つのステップで解説します。
この記事を参考にして、お子さんに教えていくと,
何も教えていない他の子よりは、早く片づけが身につくはずです。
実際にこのやり方で、お片づけを教えてきた現在6歳のむすこは,
スッキリしたお部屋の気持ちよさがわかるようになり,
自分の勉強道具やおもちゃをきちんと片付けできるようになりました。
今日からすぐに実践できるので、ぜひ試してみてください。
※これは「今すぐ片づけができるようになる魔法」ではなく,片付け・整理の本質の教え方です!
片付け・整理の本質を教えるメリット
ママに言われた通りにお片付けをしている子供たちは今
言われたことをただやっているだけ
の状態です。
このままでは、自分で持ち物を管理する年齢になったとき,
勉強道具がごちゃごちゃになり,勉強に身が入らなくなるかもしれません。
片付け・整理の本質を小さいうちから教えておくと,子ども自身にはこんなメリットがあります。
- 自分で整理整頓できるようになる
- 「いる・いらない」の判断力がつく
- 勉強に集中できる環境づくりができるようになる
- 成績がのびる
- 将来の仕事の効率アップにつながる
また、
何度も「片づけて!!」なんて言わなくてよくなるので負担が減ります。
家がきれいだとイライラも激減!
正直,デメリット、ないですよね???
片付け・整理整頓は,できて損することはないんです。
子供に片づけを教える時の4ステップ
おもちゃを例にして片付けを教えていきます。
4つのステップはこちら。
- 「どうしてお片付けをするのか」を子どもと一緒に考える【大事】
- きれいなお部屋の気持ちよさを伝える
- おもちゃを整理する
- おもちゃの収納場所(おもちゃが帰るおうち)を決める
それぞれ詳しく説明します!
【1】「どうしてお片付けをするのか」を子どもと一緒に考える
まずは
「どうしてお片付けをするか知ってる?」
と子どもに聞いてみましょう。
ゆっくりおやつでも食べながら,ママも一緒に考えます。
ところで…
大人と子供はお片付けに対するイメージが真逆
なんです。知ってますか?
子供が思うお片付けのイメージ=遊ぶのおしまいの合図・楽しくはない
大人が思うお片付けのイメージ=散らかった部屋がスッキリして気持ちがいい
大人でも例えば「換気扇掃除」とか,やらなきゃいけないけどやりたくないことを始めるのは腰が重くなっちゃいますよね。
子どもも同じで,なかなかお片付けをしてくれないのはやりたくないからです。
大人は経験から「やらなきゃいけない理由」を知ってるので頑張れます。
子どもがお片付けをがんばるためにはまず「やらなきゃいけない理由」をきちんと知っておく必要があるんです。
「どうして片づけをしないといけないのか」の答えは「家族みんながおうちで気持ちよく過ごせるようにするため」だと私は考えています。
みんなが気持ちよくおうちで過ごすためにはお掃除が必要ですが,散らかったままでは掃除をする人が困ってしまいますよね。
大人が考える「片づけをしないといけない理由」は色々あります。
ママはこう思ってるから片付けしてほしいんだ~とママの気持ちを伝えてみてください。
例えばこんな感じで。
- きれいな部屋でご飯を食べたいから
- おもちゃが落ちてると掃除機がかけにくいから
- おもちゃを踏んだら痛いし危ないから
- 約束した時間を守れる子になってほしいから
3~5歳は自分が中心の考え方をする時期です。
でもきちんと話せば「片付けるとママが嬉しいんだ」ということを理解してくれます。
【例】我が家の場合
ママ「お片付けってどうしてしないといけないか知ってる?」
5歳のむすこ「もったいないおばけが持っていっちゃうから!!」
ママ「(絵本かな?)へぇ~!なるほど~^^そうかもしれないね(笑)ママはね,毎日お掃除するときに,おもちゃが落ちてると困っちゃうからお片付けしてほしいんだ~~」
むすこ「なんで困っちゃうの?」
ママ「掃除機でおもちゃ吸い込んじゃうかもしれないし,掃除機もおもちゃも壊れたら嫌だし,ママは腰が痛いからおもちゃどかすの大変なの(笑)」
むすこ「そっか(笑)じゃあ〇くんがやってあげる!」
ママ「(やってあげる?まあいいか。笑)ありがと~♡」
【2】きれいな部屋の気持ちよさを伝える

次は,きれいなお部屋の良さを伝えます。
【やること】
- おもちゃを全部出してOKにして一日全力で遊んでもらう。
- 散らかった状態を写真に撮る。
- ママも一緒にみんなでお片付けをする。
- 綺麗になった状態を写真に撮る。
- 子供にどっちが気持ちいいかな?と聞く
- ママはキレイなお部屋が気持ちいいと思ってることを伝える
きれいな部屋で散らかっていた状態を想像するのって子どもには難しいんです。
ビフォーアフターを写真に撮って見せることで「違い」がわかるようになります。
「おもちゃがたくさん見えてるほうがいい!好き!」
という子もいるかもしれませんが,
そういう場合は「そうなんだね^^!」と気持ちを認めてあげてください。
大人だって,コレクションしたフィギュアに囲まれている方が幸せ!という人もいますから。
そんなときは
「ママはこっちが好きかな!きれいだからダンスもできちゃう♡」
というように,きれいな部屋のいいところを教えてあげてください。
このステップの目的は,きれいな部屋の気持ちよさを伝えることです。
子ども自身がきれいな部屋の気持ちよさをわかってくれたらラッキーです^^
期待しすぎず、自分の気持ちを伝えてみてくださいね。
【3】おもちゃの整理をする

次はおもちゃの整理をします。
「いるいらない」の判断力をつける練習です。
【おもちゃ整理のやり方】
- 収納ボックスの中身を全部出す
- 最近遊んでいないおもちゃを選んでもらう
- 「今までありがとう」と言っていらないおもちゃを手放す
- これからも遊ぶおもちゃを収納ボックスにもどす
子どもは大人よりも集中力がないので,一気にたくさんはできません。
燃えるごみの日の前日などに
「今日はおままごとセットを整理しよう」
「今日は工作を整理しよう」
このように、小さいところからトライしてみてください。
燃えるゴミの日が月曜日なら、日曜日は必ず1か所整理する、なんて決めるのがおすすめです。
一気にやるより、ほんの少しの「整理」を頻繁に何度もすると、より効果的です(こちらが負担にならない程度にね^^)
子供は「自分のモノを捨てる」という経験をしたことがないので,最初は「捨てる」と決めるのが難しいです。
そういう場合は無理に捨てなくても大丈夫なので
例えばこんなことを話しながら一緒に整理してみてください。
- 最近これで遊んでないみたいだけどこれからも遊ぶかな?
- 遊んでもらえないおもちゃはかわいそうだから,別の人に遊んでもらうのはどうかな?
- おもちゃのおうちはここだけだから、入れない子はかわいそうだよね。
- 遊ばないおもちゃには「今までありがとう」って言ってさよならしようねー!
↑こんなふうに書きましたが、なんとかして捨てさせよう…!とは思わなくて大丈夫です!!
繰り返していくと、だんだんわかってくるんです子供も。
何度も整理するたびに、使っていないおもちゃをボックスに戻すことになるので、自然と考えるようになります。
だから焦らないでくださいね。
うちのむすこは3歳ころから一緒におもちゃの整理を練習してきましたが最初はやっぱりどれも手放せませんでした。
でも5歳にもなると,赤ちゃんだったころのおもちゃは「もうお兄さんになったから遊ばないよ^^!」と自分で手放すことができました。
「もう遊ばないからさよならする」という判断をすることができたら、それはもうすっごい成長だと思ってくださいね!!
どうしても手放せない…!というおもちゃは,ママが保管しておいてもいいですし,「売る・寄付する」という方法もあります。
また、写真に撮って,おもちゃや作品フォルダを作ってあげて実物は手放すという方法も効果的ですよ!
【参考】【子どもの作品収納】ルールを決めて大事に保管!手放す前に写真と動画を撮っています
【4】おもちゃの収納場所(帰るおうち)を決める

子どもが片付けやすく遊ぶときに取り出しやすい収納を考えて準備します。
子どもが片付けやすいおもちゃ収納のポイントは
「細かく分類しすぎない」
「投げ込み収納」
「色分けやラベリングで片付ける場所が一瞬でわかる」
です。
カラーボックスサイズくらいの収納ボックスが使いやすいですよ^^
わかりやすい収納場所(おもちゃの帰るおうち)を決めてあげると,そのやり方を子どもが大きくなってから真似します。
ママが決めた収納ボックスから,おもちゃがあふれたら「持ちすぎ」なのでステップ3の整理をまたやってみてください^^
4つのステップを何度も繰り返します
子供に「お片付け」を教える4つのステップをもう一度まとめます。
- 片づけをする理由を子どもと一緒に考える
- きれいなお部屋の気持ちよさを伝える
- おもちゃの整理をする
- おもちゃの収納場所(おもちゃが帰るおうち)を決める
子供は覚えるのが早いけど忘れるのも早いです。
ステップ1と2は時々聞いてみたり
「きれいなお部屋は気持ちいいなぁー!」
なんてつぶやいてみてください。
ステップ3のおもちゃの整理は定期的に繰り返します。
収納方法は常にアップデートを意識してみてください。
使いにくそうなところを直したり,ラベリングをかき直したり。
簡単に楽しく片づけられるようにしてあげるといいですね。
- 色別の収納ケースを使う
- ざっくり放り込む収納にする
- 写真やイラスト付きのラベリングをする
- 子供の目線の高さに収納する
こういう工夫をすると、子どもは片づけやすくなります。
収納のやり方は,幼稚園や保育園をのぞいてみると発見があったりしますよ!
保育現場は子供が自分たちでお片付けができるようにいろんな工夫をしているんです。
よかったら参考にしてみてください♪
まとめ
お片づけは子どもにとって、まったく楽しいコトではありません。
まずはその考え方を修正してあげてください。
親が一緒に取り組める年齢のうちに,「片付けに対する考え方」と「整理の基本」を身に付ければ、きっとお片づけができる子になります^^♪
\この記事もあわせてぜひ/


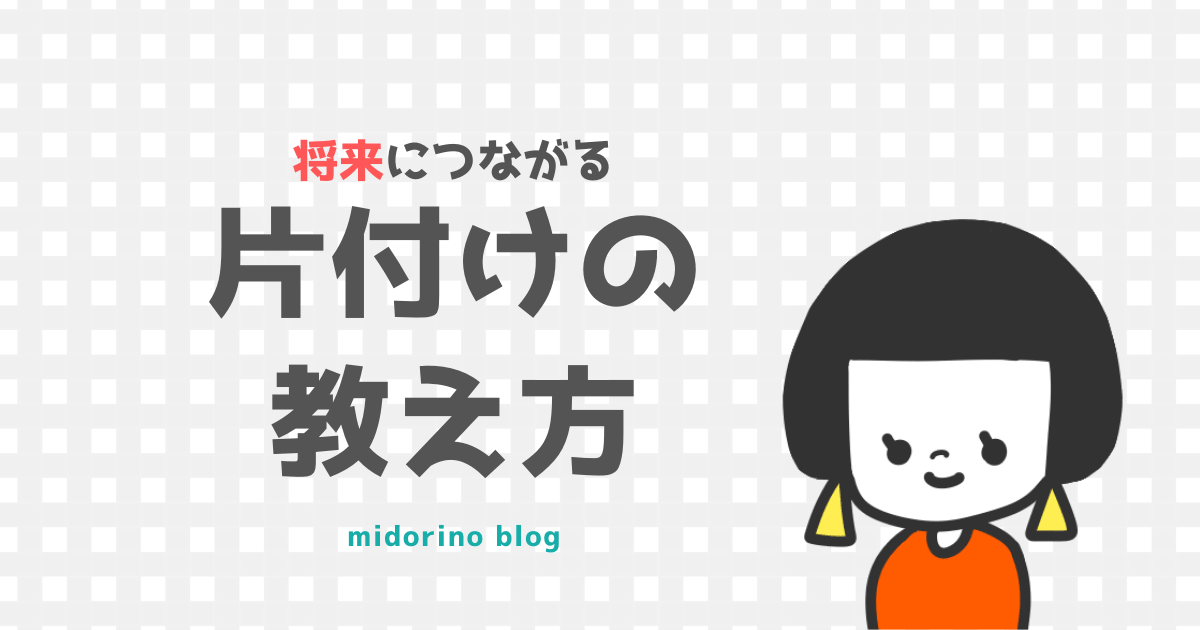
.jpg)
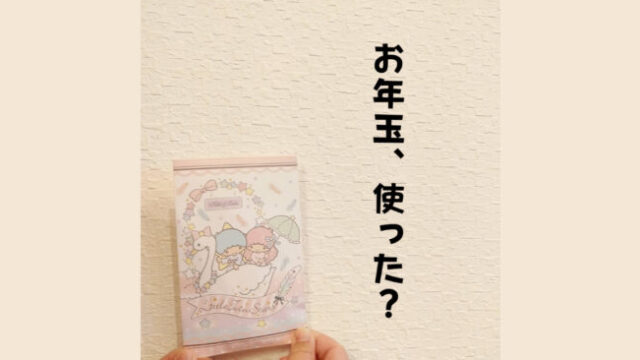
-640x360.jpg)